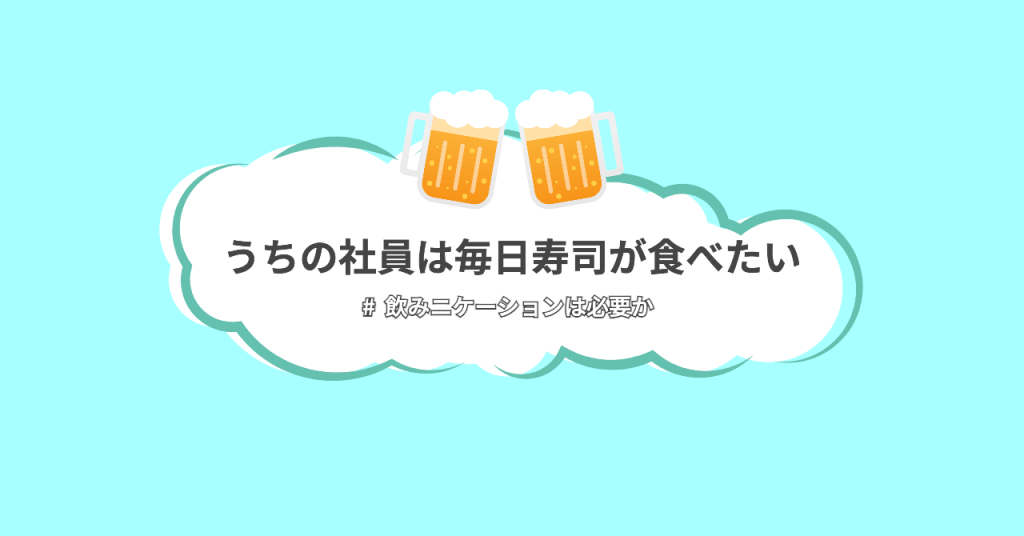
題名の通りうちの社員はお寿司が大好きで毎日でも食べられるそうです。
そんな社員のリクエストで弊社で行っている月末の決起会は、お寿司屋さんになることが多いです。
このように毎月決起会を行なっていますが、ここでよく話題に上がる「飲みニケーション」について私なりの考えをまとめてみました。
そもそも飲みニケーションをGoogle検索すると『職場の同僚や上司・部下などとお酒を飲みながらコミュニケーションを取ること』と書いてました。
どうやらアルコールにより脳を麻痺させることが抑止力を低下させ、本音での会話やチームワーク強化につながるようです。
いざ科学的な観点から説明されると少し受け入れ難くなりますね。
先日の会食で「やっぱりお酒を一緒に飲まないと関係性の構築って難しいよね」と言われたのを思い出しました
後に同じことを社員に言うと「最近の若い子は会食や飲み会が好きじゃないない人も結構いるみたいです。」と衝撃の事実を聞かされました。
結論から言うと私は賛成派です。お酒を飲んで本音で話せる中ではないと相手の本性が分かりにくくうまくやっていけないと思っています。
しかし、ご安心を、お客様にもお取引先様の中にも一緒にお酒を飲んだことがない人が大半です。
逆にお酒を交わさずにお取引していることが当たり前です。
ただ私の見解として、むしろ上司とは積極的に飲みに行った方がいいと思います。
理由はシンプルで仕事の話を仕事以外の時間で聞けるからです。
もし、あなたが人よりも仕事ができるようになりたいと思っていても会社にいられる時間は限られており、同期との差別化を図るのは難しいです。
しかし、一度先輩や上司と飲みに行くといろんな仕事の失敗談や成功談が聞けます。
そこでいわゆるその失敗や成功の擬似体験をするのです。
特にこの擬似成功失敗体験は経験の少ない若い社員にとっては非常に意味のあるものです。兄弟で言うと兄や姉より妹や弟の方が要領が良いことと一緒です。
私は長男で要領が悪かったと感じていたため、前職の社内では特に意識して擬似体験をしようと心がけています。
場所は飲み会、休憩中、営業同行の移動中、さまざまなところで先輩の失敗談や意見をとにかくよく聞きに行きました。
話は会食に戻りますが、上下関係以外にも会食は有効的です。
例えばお互い普段は別部署で仕事を引き継ぐだけの関係性でも会食を通して会話する機会が増えたとします。今まではただの流れ作業が、会食をきっかけに意見が出しやすくなり、一緒に新しいアイデアを生み出し生産性が上がるというようなことはしばしば起こります。
なので、さまざまな会社の福利厚生を見ても会食や女子会が中に入っていたりするのではないでしょうか。重要なことは「お酒を飲むこと」ではなく「仕事以外にプライベートな時間を設けること」だと感じます。
個々の強固なつながりがやがてチームになり、部署になり会社になります。
まあ、読んでもらうだけではなかなか分かりづらいので一旦お酒でも飲みながら話しましょ。
ということで今回の投稿は終わりになります。
これからも毎週投稿していくので来週も読んでください。ありがとうございました。
中村 龍之介
